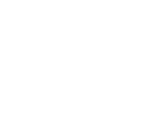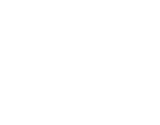ADHD注意欠陥・多動性障害の子どもと大人の栄養や食事と行動
ADHDと聞くと、多くの人が、落ち着きがない、集中できないなどの特徴を思い浮かべるかもしれません。
しかし、ADHDの子どもだけでなく大人たちは「食べること」にもさまざまな困難を抱えていることが少なくないようです。
どのような現実があるのでしょうか。
体の発育に違いがあった?
インドで行われたある研究では、ADHDと診断された子どもと、そうでない子どもを比較して、栄養状態や食事中の行動にどんな違いがあるかを調べました。
対象となったのは、4歳から12歳までの子ども108人で、そのうち54人がADHDの診断を受けており、残りの54人が定型発達児でした。
まず研究者たちは、子どもたちの身長や体重、そして中上腕囲(腕の太さ)を測りました。
すると、ADHDの子どもたちには次のような傾向が見られました。
-やせている子どもが多い
-身長が同年代の平均よりも低い子が多い
-中上腕囲が小さく、筋肉量が少ない傾向
これらはすべて、栄養が足りていない可能性を示しています。
特に、ADHDの子どもの半数以上が「中上腕囲が低栄養レベルにある」という深刻な結果だったようです。
食事の場面でも困難がある?
さらにこの研究では、子どもたちの食事にまつわる行動にも注目しました。
保護者にアンケートを実施し、以下のような行動がどの程度見られるかを調べたようです。
-食事中に立ち歩く
-食べるのがとても遅い
-食事に集中できない
-好き嫌いが多すぎる
-食べ物にあまり興味を示さない
この調査の結果、ADHDの子どもの約3人に1人が、こうした摂食の困難を抱えていることがわかりました。
一方で、定型発達の子どもではこの割合は約9%となっており、と大きな差がありました。
ADHDの子どもへの支援で大切なこと
さらなる分析の結果、食事の問題を多く抱える子どもほど、体重や身長、腕の太さが低い傾向が報告されています。
つまり、うまく食べられないことが、栄養不足や発育の遅れに直結しているということのようです。
ADHDの子どもに対しては、行動や学習の支援だけでなく、食事や栄養の視点もとても重要です。
保護者や周りの大人にできることには、次のようなことがあります。
-成長曲線を定期的にチェックする
-食事中に集中できる静かな環境をつくる
-一度に食べさせる量を減らし、回数を分ける
-無理に食べさせず、プレッシャーを与えない
-栄養士や小児科医に相談して、必要な支援を受ける
食べないことがわがままだと決めつけるのではなく、「この子なりの困りごとがあるのかもしれない」と考えることが、支援の第一歩と考えられそうです。
食べることの大切さ
食事は、子どもの体を育てるだけでなく、家族との大切な時間でもあります。
ADHDを持つ子どもにとって、食べることが苦痛な時間になってしまうと、心の面でも影響が出てくるかもしれません。
だからこそ、大人のまなざしとサポートが必要です。
なかなか食べ終わらない、いつも好きなものしか食べない、椅子にじっと座っていられないといった様子が見られたら、それは発達のサインかもしれません。
早めに気づき、工夫しながら支えてあげることが、子どもの元気な成長につながるのではないでしょうか。
子どもの体も心も、日々の食事からつくられていきます。
栄養は、筋肉や骨になるだけでなく、脳の働きや感情の安定にも深く関わっています。
だからこそ、何を、どう食べるかは、子どもの未来をつくる大切な土台です。
ADHDという特性を持つ子どもたちにとって、食べることそのものが難しい場合もありますが、理解し、寄り添い、小さな工夫を重ねることで、食べる力は少しずつ育っていきます。
私たちの体と心は、毎日食べるものでできています。
だからこそ、困難なことも多いと思いますが、食べることを大切にすることが、子どもたちの健やかな成長を支える第一歩になるのではないでしょうか。
関連する記事:
子供のメンタルヘルスは食べ物や自然とのふれあいで改善できる?
ADHDや自閉症スペクトラム障害の子どものための栄養素
注意欠陥多動性障害 (ADHD) の症状を引き起こすトリガーには亜鉛欠乏症や食品添加物も?
お問い合わせはこちらから
受付時間 am9:00-pm5:00/土・日・祝日除く
引用文献:
Nutritional status and feeding problems in pediatric attention deficit-hyperactivity disorder