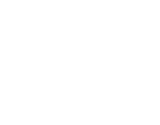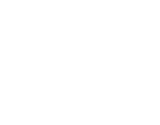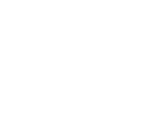鮭の栄養と養殖鮭と天然鮭の違い?
鮭は、季節を問わず手に入りやすく、調理も簡単でバリエーション豊かな料理に使えることから、世界中で親しまれている魚のひとつです。
近年では、鮭が持つ豊富な栄養価にも注目が集まっており、健康志向の人々の間でも人気が高まっています。
そんな中、天然ものと養殖ものの鮭には、栄養面や安全性などで違いがあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
実際、現在市場に出回っている鮭の多くは、漁獲によるものではなく、養殖場で育てられたものが中心となっているのが現状です。
では、養殖と天然の鮭にはどのような違いがあると考えられているのでしょうか?
Contents
1.鮭の栄養は?
鮭は、大変栄養価の高く、主に次のような栄養が含まれます。
-オメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸は、脳の働きを活発にし、記憶力や学習力を高めると言われています。
また、動脈硬化を防ぐことで、心臓病の予防にもつながる可能性があるとして注目されています。
-アスタキサンチン
最近特に注目を集めているのが、アスタキサンチンです。
アスタキサンチンは、サケ科および甲殻類の持つ赤やピンク色を提供するカロテノイドです。
アスタキサンチンは、抗酸化活性を持っているため、アンチエイジングを目指す方には気になる成分の一つです。
また、心血管疾患の予防、免疫力の強化、ヘリコバクターピロリ対策、白内障の予防などにも、アスタキサンチンは関連しています。
鮭には他にも、
などの栄養素が豊富に含まれます。
2.天然と養殖の栄養の違い
一般的に、天然の鮭は養殖ものに比べて、カロリーや飽和脂肪、ビタミンAおよびDの含有量がやや少ない一方で、たんぱく質を多く含む傾向があると報告されています。
オメガ3脂肪酸の含有量については、鮭が摂取するエサの内容によって左右されますが、ワシントン州保健局によれば、養殖鮭の方が脂肪分が多いため、同じ量の切り身で比較すると、天然鮭と同等の量のオメガ3が含まれているとされています。
また、アスタキサンチンに関しては、養殖鮭には合成のアスタキサンチンが添加されたエサが使われています。
養殖由来のアスタキサンチンは、天然のものに比べて抗酸化力がやや劣るとされていますが、それでも身体にとって有益な成分であると考えられています。
また、天然と養殖の違いとして、残留性有機汚染物質と重金属が含まれるかどうかも重要です。
残留性有機汚染物質とは、農薬や医薬品、工業用化学物質などに含まれる人工的な有機化合物で、自然界で分解されにくく、長期間環境中に残り続ける性質を持っています。
これらの物質は動物の体内、特に脂肪組織に蓄積されることがあり、脂肪分の多い魚には比較的高濃度で含まれている可能性があると報告されています。
養殖された鮭は、野生の鮭よりも有機汚染物質の含有量が少ない傾向があるようです。
近年の研究では、野生のタイセイヨウサケの方が、養殖サーモンよりも高濃度の有機汚染物質を含んでいることが示されています。
この差は、野生の鮭が生息する海洋環境における汚染の影響によるものと考えられています。
また、水銀などの重金属は、人体に酸化ストレスを引き起こす可能性があります。
研究によると、野生のタイセイヨウサケは養殖のタイセイヨウサケよりも多くの水銀を含んでいたという報告もありました。
このように、重金属含有量の観点から考えた場合は、天然の鮭の方が養殖に比べて汚染物質や重金属を含んでいる可能性が高いと考えられそうです。
まとめ
天然の鮭と養殖の鮭を比べると、栄養面では天然ものがやや優れているとされる一方で、養殖鮭のほうが汚染物質や重金属のリスクが低い傾向にあるようです。
現在ではどちらも安全に食べられるとされており、養殖鮭も短期的には栄養価の高い食品として安心して取り入れられることがわかっています。
参照情報:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322847
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16431409/
2025年4月20日 記事を更新いたしました。