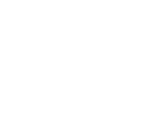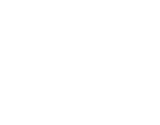食物繊維が豊富な食事と人間の腸内微生物叢と世界の地域特性
人間の腸内細菌についての国際的な研究報告について、以前もご紹介させていただきました。
それによると、アフリカで健康上の問題となっている栄養失調や、アメリカでの問題となっている肥満やメタボリックシンドロームはいずれも腸内細菌叢のバランスの悪化が原因となっていることがわかりました。
さらに元をたどると、母乳に含まれるオリゴ糖が影響していることがわかりました。
地域性とその地域での健康問題と腸内細菌の関わり合いは大きいようです。
今回は、ヨーロッパとアジアの地域での報告をご紹介したいと思います。
脂肪の高摂取と牛乳の低消費
ヨーロッパの食事は非常に多様です。
中でも最近は脂肪の高摂取と牛乳の低消費など、食事の西洋化に向かう傾向にあり、これはヨーロッパ諸国での健康問題を引き起こしていると考えられています。
例えば、肥満、心血管疾患、結腸癌などの発生率の上昇などにもつながります。
これらに対応するために様々な研究がなされています。
ナッツ(特にクルミ)は、その摂取により血漿脂質レベルを低下させることが示されたという点で健康上の利点があることで知られています。
クルミの摂取と、腸内微生物叢の組成との関連についての96人の健康な参加者を対象としたランダム化比較試験では、クルミの摂取がプロバイオティクスや腸内微生物叢の調整を促進する可能性があることがわかっています。
一方、ビタミンと食物繊維が豊富な菜食主義の食事は、免疫系に有益であることが示されています。
菜食主義の長期的な食事パターンが腸内微生物叢集合の主要な原動力であるという考えも支持されています。
ご存じのとおり、腸内細菌群にはその餌となる食物繊維が必要です。
これらの結論として、菜食主義の食事への切り替えは、腸内微生物叢組成に影響を与えることがわかっています。
低脂肪高炭水化物食から高脂肪低炭水化物への変化
アジアの研究では、低脂肪高炭水化物食から高脂肪低炭水化物への変化が問題視されています。
さらに、中国の伝統的な食事が2型糖尿病のリスクから身を守る可能性があることが示唆されています
中国では、伝統的な低脂肪、高炭水化物食から比較的脂肪が高く炭水化物が少ない食事への栄養転換が行われてきました。
その結果、過去30年間に肥満、2型糖尿病、心血管疾患、結腸癌のリスクが劇的に増加したとみられています。
さらに研究によると、高脂肪食と炭水化物の割合が比較的高い伝統的な食事を比較すると、ヒトの腸内微生物叢の多様性と豊かさが関係することが示されています。
伝統的な漢方薬であるGegen Qinlian Decoction(GQD)は、2型糖尿病を緩和すると考えられています。
また研究によると、1日あたり5グラムの用量で別の漢方薬であるDSGを14日間投与すると、ビフィズス菌や乳酸菌などのプロバイオティクスが有意な増加を見せたそうです。
さらに潜在的な病のもとであるウェルシュ菌の顕著な減少により、腸内微生物叢を有益に調節できることが判明しました。
DSGはまた、便秘の患者の腸機能を効果的に改善し、排便頻度を週1.78回から週3.02回に著しく増加させる可能性があるとも示されています。
まとめ
腸内微生物叢の変更が私たちの健康を改善し、病気を予防および治療するためにどのように使用されるかを見極めるにはさらなる研究が必要といえます。
しかしながら、繊維が豊富な食品による、ヒトの健康に対する微生物叢の変化の重要性はどの国や地域においても、その国における代表的な健康上の問題との関係においても、またそれ以外でも重要視されていることがわかりました。
関連記事:
2型糖尿病の食事例に低GIの低炭水化物食ダイエットがおすすめされる理由?
子供や赤ちゃんの健康とアレルギーから発達障害予防に大切な6つのおすすめ
お問い合わせはこちらから
受付時間 am9:00-pm5:00/土・日・祝日除く
引用文献:
Diet and the Human Gut Microbiome: An International Review