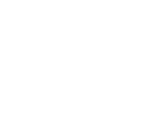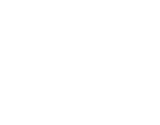睡眠時遊行症(夢遊病)の原因や予防法を考える
夜はぐっすりと熟睡したいものですが、睡眠時遊行症(Sleepwalking)、または夢遊病に悩まされる方も一定数いるようです。
夢遊病と呼ばれるような現象は、「パラソムニア」と呼ばれる睡眠障害の一種です。
これは、睡眠中に望ましくない行動が起こる症状の総称であり、本人の意識とは無関係に身体が動くのが特徴です。
通常、私たちが眠っているとき、脳と身体の活動は休止状態にあります。
しかし、睡眠時遊行症では、身体と一部の無意識的な脳の活動が残ったまま、意識がない状態で歩いたり行動したりするのだそうです。
夢遊病の原因や予防法などについて探ります。
睡眠時遊行症の主な特徴
睡眠時遊行症(夢遊病)には次のような特徴があるようです。
-子どもによく見られる:特に8〜12歳の間に多く、最大で17%の子どもが経験するとされています。
-成人でも発症する:およそ4%の成人も夢遊病を経験する可能性があります。
-多くのエピソードは10分程度で終わるが、より長時間続くこともある。
安全確保のため、周囲の人が見つけたら、優しく誘導してベッドに戻すことが重要のようです。叫んだり驚かせるのは避けるようにしましょう。
子どもにおける夢遊病は、通常治療不要で見守るだけでよいとされています。
一方、成人で初めて発症した場合や、危険行動を伴う場合は、早めに睡眠医学の専門医に相談することが勧められます。
睡眠時遊行症の原因
研究によると、睡眠時遊行症は「ノンレム睡眠(深い眠りの段階)」の最初の1/3のタイミングで起こりやすいとされています。
そのため、脳の睡眠サイクルの異常が関与していると考えられています。
また、以下のような要因が関係している可能性もあるようです。
-遺伝:家族に同様の症状がある場合、発症しやすい。
-睡眠不足:深い眠りが増えると、発症のリスクも上昇。
-ストレスや環境要因(騒音や光など)
-アルコールの摂取
-睡眠時無呼吸症候群
-薬剤(特に睡眠導入薬ゾルピデムなど)
-発熱、偏頭痛、旅行、PMS(月経前症候群)
-脳の損傷や脳卒中
睡眠時遊行症の症状
夢遊病の明確な特徴は、眠っているのに歩いたり行動したりしていることです。
また、他の代表的な症状には次のようなものがあるようです。
-目が開いていて、ガラスのようにぼんやりとした視線
-起こしにくい、または起こすと混乱する
-眠ったままの状態で喋る、つぶやく
-食事やトイレ、性的行動を無意識に行うことも
-翌朝、本人は何も覚えていないことが多い
まれに、自動車の運転など非常に危険な行動をとることも報告されています。
このような場合や、階段や鋭利な物が周囲にある場合は重大な怪我のリスクもあります。
治療法にはどのようなものがあるのでしょうか。
睡眠時遊行症の治療法
-子どもの場合
多くのケースで、子どもは成長とともに自然に症状が改善するようです。
そのため、特別な治療よりも安全管理が優先されます。
効果があるとされる方法の一つに「スケジュール覚醒法」があります:
子どもが夢遊病を起こす時間を記録
その15分前に優しく起こす
軽く目を覚まさせた後、再び寝かせる
これを1ヶ月間毎晩繰り返すことで、症状の改善が期待できるようです。
-成人の場合
成人の場合、まずは睡眠日記の記録や睡眠検査(ポリソムノグラフィー)を受けることが推奨されます。
睡眠時無呼吸症候群や他の睡眠障害がある場合、それを治療することで睡眠時遊行症が改善することもあります。
また、催眠療法が有効だったという報告もあります。
なお、薬物治療は一般的ではなく、安全な睡眠環境の確保が非常に重要となるようです。
予防法
睡眠時遊行症の予防には、以下のような対策が効果的とされています。
-規則正しい睡眠習慣の維持(毎日同じ時間に寝起きする)
-睡眠不足の回避、特に時差のある移動の際は注意
また、睡眠環境の安全確保には次のような方法があります。
-窓やドアにロックをかける
-鋭利な物やガラス製品を寝室から取り除く
-階段にゲートを設置、低いベッドを使用
-車の鍵や刃物、工具などを手の届かない場所に保管
-薬剤確認(普段の薬が睡眠時遊行症を引き起こす可能性があるか)
-ストレス管理(就寝の5~6時間前に軽い運動を行うと効果的)
まとめ
睡眠時遊行症は、特に子どもに多く見られる症状ですが、成人にも起こりうる現象です。
本人や周囲にとって危険を伴うことがあるため、安全な環境作りと生活習慣の見直しがとても大切です。
症状が重い、または生活に支障が出ている場合は、専門医の診断を受けることも大切です。
関連する記事:
睡眠時無呼吸症候群と脳の健康アルツハイマー型認知症の共通点!?
睡眠時間と脳の働きにおすすめの食べ方と栄養素
産後うつや産後不安を軽減する薬以外の方法とは?
お問い合わせはこちらから
受付時間 am9:00-pm5:00/土・日・祝日除く